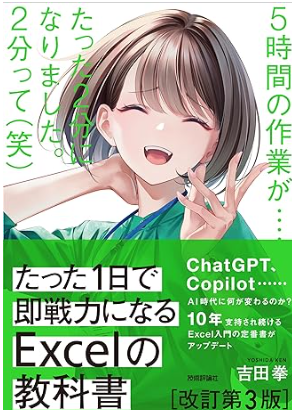

Tea Time ちょっとひと息いれよう
「漢字にすれば丁寧」って、ほんとうにそう?
実は、それ、よくある日本語の誤解なんだと私は思います。
たとえば「して置く」「読んで見る」――こう書くと、ちょっと頑張った(変換した)感じは出るのだけれど、実は逆効果なことも。
今回は、文章がグッと読みやすくなる“ひらがなのちから”についてお話しします。
本記事では、具体的な例で、その読点の効果を紹介したいと思います。
例1:『おく』には2つの顔がある
「おく」には大きく分けて2つの使い方があります。
本動詞としての「置く」
→「机の上に本を置く」のように、実際に何かを置く動作を表す。
補助動詞としての「おく」
→「確認しておく」「保存しておく」のように、「前もって〜する」「〜した状態にしておく」という意味を補う役割。
この2つ、見た目は同じ「おく」ですが、役割が違います。
📌 添削前:「会議の前に、この件について触れて置こうと思います。」
✏️ 添削後:「会議の前に、この件について触れておこうと思います。」例2:『みる』には2つの顔がある
📌 添削前:「先輩の指示通りに、とりあえずやって見る。」
✏️ 添削後:「先輩の指示通りに、とりあえずやってみる。」例3:『いく』には2つの顔がある
📌 添削前:「時代とともにこの伝統も忘れられて行くのだろうか。」
✏️ 添削後:「時代とともにこの伝統も忘れられていくのだろうか。」漢字変換できそうなものはすべからく変換すれば良いというものではない!
と私は叫びたい!(笑)

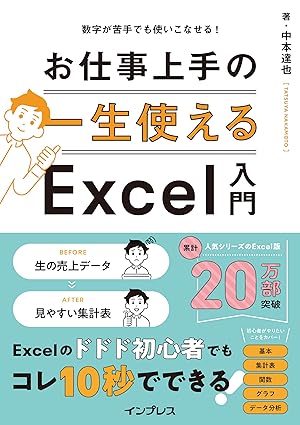


コメントを残す